 |
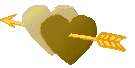 |
|||||||
| 愛してるのはあなただけ | ||||||||
 |
||||||||
| 「では、各自指定のプリントを始めろ、今日は一日オレがもらってるから、好きな時間に休憩をとるように、質問はいつでも受け付けるからな。」 静かな教室にセフィロスの魅力的なバリトンが響く。 もう、受験シーズンも追い込みにきている2月、なかには進路の決まっているものもいる。 「先生、オレたちのプリント、これなんです?」 一人の男子生徒が、自分のプリントをひらひらさせて聞いてくる。 当然だ、他の生徒はきちんと五教科の内容が書いてあるプリントなのに、一部の生徒だけどう見ても勉強とは関係ないプリントをもらってるのだ。 「ああ、進路の決まっている奴は、今さら勉強する気にはならんだろ?かといって遊ばせるわけにはいかんらしいから、一般常識クイズだ。 知っていたら、卒業しても役に立つぞ、全部書き終わったら、そこのノートパソコンに答えを入力してみろ、ゲームが始まる。」 「ゲーム?」 「そう、その答えの通りにおまえが行動したら、どういう人生を送れるかのシュミレーションだ。 ちゃんと、フォローアップも教えてくれるから、がんばってみろ。」 「ずるーい、私たち、勉強してるのに遊ぶ人たちがいるんですか?」 別の女生徒から、非難の声があがる。 「別にそっちをしたければ構わんぞ、立派な社会勉強だし、本番前の貴重な時間をどう使うかはお前の自由だ、オレは指図せん。」 言われて、その女生徒は赤い顔をして自分のプリントを始める。 セフィロスの指導方針 『各自にあったものを、各自のペースで、そして自分で考えて選ぶ事。』 だから、選んだ結果は自分のせいであり、親のせいでも学校のせいでもない。 ただし、迷ったらいつでも相談に乗る。 出した結果が明らかに間違っていても、頭ごなしには言わない、どうしたらそういう結論に達したのか聞いてくる。 そして、それが『逃げ』から来たものでないのなら、一件無茶と思える事でも支持してくれるのだ。 とても成績のよい女生徒がいた、親はもちろん誰もが有名進学校に入る事を疑わなかった。 しかし彼女は、某有名女性だけの歌劇団に入りたかったのだ。 幼い頃からそれを夢見て、ピアノやバレエを習ってきたのに、中学を卒業するとそこの付属の学校に入りたいと言うと、親は烈火のごとく反対した。 それを支持してきっちり説得したのはセフィロス。 彼女は無事100倍といわれる難関を突破して、春から、そこの劇団の学校に通う。 サッカーが好きで高校に行くより、ユースに入って早くプロになりたいと言う男子生徒もいた。 高校ぐらいは卒業すべきだ、という親を説得したのもセフィロス。 ただし、明らかに本気で無いものには、たとえ子供でも容赦のないセフィロスの毒舌が飛んでくる。 だから、このクラスはだれよりも担任を信用している。 それゆえに、今日のこの日は心を込めて、先生が一番喜ぶものをクラス全員でプレゼントしたのだ…赤いリボンを大事にかけて… 「おい、オレも進路決まってるんだけど…」 赤いリボンをしたオレが不機嫌に口を開く。 「ちょっと聞いてるのかよ?オレだけなんでこんな目にあってるんだ!?」 にっこり笑顔でセフィロスは答える。 「それはお前がオレへのプレゼントだからだ。」 おでこにchu!と音をたてるキスをすると、周りからクスクス笑いや、口笛が飛ぶ。 憮然とするオレは、教卓に座るセフィロスの膝の上…荷物宜しく赤いリボンでぐるぐるまきにされている。 「せっかくのクラス全員の好意を無駄にするわけにはいくまい?」 にやりと笑って、セフィロスは腰を抱く手に力を込める。 「オレの人権は?」 「今日ストライフの人権はないと思う奴手をあげろ。」 一斉に上がったクラス全員の手を見て、脱力して机に突っ伏した。 …もう!みんなおもしろがって!! 「というわけで、今日一日おまえはオレのものだ。」 そう、今日はバレンタインデイ。 何も知らないオレは、いきなりクラスのみんなにリボンでぐるぐるまきにされ、セフィロスに『プレゼント』されてしまったのだ。 喜んだセフィロスが速効で膝の上に乗せて、授業を始めたもんだから、生徒達は大いにはしゃいだ…オレ以外は… …だって困るじゃないか… セフィロスのつけるコロンの匂い、背中に触れる体温、耳に触れる吐息… ドキドキする、だって学校でこんなに近くでセフィロスを感じた事なかったから… 母亡き後、セフィロスと同居しているのは校長だけが知っている、不公平感を与えてはいけないという理由で、他には内緒だ。 そしてもちろん、二人が恋人同士であると言う事は誰も知らない。 家の中ではこのくらい近付くのは別に恥ずかしい事ではない、むしろ離れているときの方が珍しいくらいだ。 だけど、学校では… 悪戯なちょっかいを掛けてくるものの、セフィロスは『先生』という線を超えてくる事はない。 だから困るのだ、こんなに近くにいると、学校だという事を忘れてしまう、もっと触れて欲しくてしょうがなくなる。 何より夕べ抱かれたばかり、セフィロスの銀色の髪がさらさらと音を立てて頬に触れるといやでも思い出してしまう… 滑らかに肌の上を滑り、快感をくみ出す指先と唇… いつもより甘さを含んで、自分を呼ぶかすれたバリトン… そして、身体を合わせたセフィロスの、汗の混じったコロンの香り… 同じなのに、同じなのに…学校の中だと言うだけでセフィロスは抱き締めるだけでそれ以上触れてこない。 もちろんオレだって、セフィロスが触れてくれない理由くらい解っている、だからこそ、餓えたようにそれを望む自分が、たまらなく嫌らしいようで自己嫌悪に陥るのだ。 「フ…ストライフ!」 「え?何?」 机に突っ伏したまま、ほけらと答える。 「だれが寝ていいと言った?オレはこっちの英語の質問に答えてるから、おまえはそっちの数学を教えてやれ。」 先生の顔をしたセフィロスが指す方向には、プリントを持った男子生徒が頭をかいている。セフィロスはというと、女生徒に英語の添削と即興の暗記の仕方を伝授している。 「どこだよ、解らないのは!?」 いささか不機嫌な声を出して、プリントをひったくった。 ぶつぶつ言いながらも、丁寧に教えだすオレを見て、セフィロスはくすりと笑う。 結局、質問しにくる生徒の1/3を膝の上のオレにまかせて、その日セフィロスは授業を終えたのだった。 「よし、今日はこれで終わり、各自今日解らなかった所は、もう一度振り返ってみる事、では解散。」 ホ−ムルームも省略して、さっさとセフィロスは生徒を帰らせる。 が、しかし… 「先生!これもらって下さい!!」 授業が終わるのを待ちかねたように、わらわらと、女生徒がセフィロスを取り囲んだ。 手には色とりどりのラッピング、いつのまにか他のクラスや学年の女生徒も混じっている。 「やっぱ、もてるよな先生。」 隣の男子生徒がうらやまし気に言った。 「ったく…チョコを用意してるんなら、最初っから人で遊ぶなよ。」 あー腹が立つ、オレは不機嫌なんだぞ。 なんだよ、嬉しそうにチョコもらっちゃってさ、そりゃぁ学校では『先生』なんだろうけど…オレのなんだぞ、勝手に触るなよ…セフィロスのバカ… それでなくても、今日一日抱き人形のように扱われ、お昼休みもしっかりセフィロスの膝の上で食べさせられたのだ。 べたべたしたいのにできない、そんなジレンマを山ほど抱えてるのに! 早く家に帰って二人っきりになりたい… 鞄を持ったオレをセフィロスは呼び止めた。 「あ、ストライフ、おまえは残れ。」 「なんで?」 どきっとして答える、同居してるのがばれない様に、一緒に帰ってはいないのだ。 「もう少し手伝ってくれ、そこのプリントを持って資料作成室に行って、いつものソフトで処理をたのむ、オレもすぐ行くから。」 「えー?オレもう帰るよ。」 セフィロスは、不機嫌を隠そうともしないオレを、ピシッと指差す。 「何を言ってる、今日一日おまえの身体はオレがもらったんだぞ、拒否権はない!」 あんまりなセリフと、にやっと笑う顔に、思わず真っ赤になって文句を言おうとするが、それよりも周りの女生徒の反応が早かった。 「きゃーvv」 上がった黄色い悲鳴に思いっきり迫力負けして、オレは渋々プリントを持って教室を出た。 パサッパサッと紙をめくる音がする、乱暴にプリントをオートのスキャナの上にセットする。 この資料作成室は、セフィロスが来るまでは誰も使っていない部屋だった。 予算の編成で最新型のパソコンがネット接続して配備されたのにもかかわらず、誰も使っていなかったのだ。 それをセフィロスは、勝手になんやかやと持ち込んで、カスタマイズし、いつのまにかマイルームと化していた。 ソフトを起動して、オートのスキャナにセットすれば、各自の苦手な設問の傾向がデーター化されて、翌日配るプリントに反映されるのだ。 …自分ですればいいじゃないか、これくらい… チョコを受け取っていたセフィロスの笑顔に腹が立つ、家で渡そうか、学校で渡そうか悩んでとうとう持ってきたチョコが鞄の中に入っている。 セフィロスが時々ブランディのつまみにしている、ビターな薄いスイス製のチョコ… 「知るもんかあんなやつ!」 思わずばさっと乱暴に紙の束を机に叩き付けると、突然後ろから抱きすくめられた。 「乱暴に扱うな。」 振り向かなくても解る、降ってくる銀色の長い髪。 「何をそんなに怒ってるんだ?」 なんとなくその言い方がしゃくに障って、ぷいと横をむくと優しく唇を重ねられた。 そのまま、オレを抱き締めたままセフィロスはイスに座る。 そして、ゆっくりと舌を絡めてくる。 オレはセフィロスの膝を跨いでイスに座って正面から抱き締められている、身体が近い…さっきまでよりも…ずっと近い… ドキドキと音がするほど跳ねる自分の心臓。 セフィロス…学校の中だよ? とまどうオレを無視して、セフィロスの舌はオレの口の中を我が物顔で這い回る。 軽く舌先で突いたかと思えば、きつく絡めて吸い上げられ、背中を撫でられる。掌の心地よさも相まって、何もかも忘れて、オレは自分からセフィロスの首にしがみつき、強請る様に身体を擦り付けた。 自然腰が揺れてくる。 だめだ、めちゃくちゃに、感じちゃってる… だってさっきまで、触れたくても触れられなかったからよけいに… この抱き締める逞しい腕も、優しい唇と舌先も、そしてコロンと混じったセフィロスの匂い…オレの物だ、全部オレだけの物だ… さっきまでのもどかしい想いが、よけいに火をつける。 溢れた唾液が口角を垂れてくるのにも構わずに、オレは夢中でセフィロスの舌に負けじと吸い付いていた。 お互いの息が上がる頃、ようやく唇を外す、糸を引いた唾液を指先で拭って、セフィロスがふっと笑った。 「我ながら、我慢がきかないな、今日一日ひどい拷問だったからな。」 セフィロスも? きょとんとしたオレの顎を持ち上げて、セフィロスが呆れた様に呟く。 「なんだ、気付いてなかったのか?一日オレの膝に座ってた癖に。」 言われてみれば、ずっと腰に何か硬い物が当たっていた様な… 「オレ、自分の事に精いっぱいで解んなかったよそんなの、だったらやめればよかったじゃないか。」 今だって、しっかり反応しているオレの分身をどうしようかと思ってるのに、だけどキスしながら無意識に擦りつけてたせいで、セフィロスもしっかり硬度を増してるのが解る…なんとなく…嬉しい… 「せっかく学校で、おまえをおおっぴらに抱き締められるチャンスを見のがす手はなかったからな、それに…」 セフィロスが言いかけて止めた。 「それに?」 「な、なんでもない。」 ちょっとバツの悪そうな顔をするセフィロス、こういう時って何かバカバカしい事を隠してるんだ。 あんまり問いつめる気分でもなかったから、オレは手を延ばして机の上の鞄を取って、中からチョコの包みを取り出した。 「さっきいっぱいもらってたから、今さらだけど、オレから。」 セフィロスはにっこり笑って、包みをほどく。 「リンツのチョコか、ありがとう。オレもホテルのスゥイートとレストランを予約してる。」 「セフィロス、バレンタイン知ってたんだ。」 「あたりまえだろ、恋人達の日だ。せっかく金曜日にこの日が来たのにたっぷり楽しまなくてどうする?」 赤くなったオレの耳元で、セフィロスがチョコよりも甘く囁く。 「今日一日、さんざん焦らされたからな、早くディナーを済ませてお前が食べたい。」 もう!どうしてこんなにオレの心をくすぐるんだ…オレもそうだよ… なんだか恥ずかしくって、ごまかす様にセフィロスに言った。 「いつもソレばっかり!せめて先にオレのチョコ一個くらい食べてよ。」 セフィロスの手の中から、箱をひったくってふたを開けると、セフィロスは、悪戯っぽい顔をした。 「食べさせてくれ。」 オレはくすっと笑って一つつまむと、セフィロスの口元に持っていった。 「そうじゃないんだ。」 セフィロスはその手を掴むと、チョコをオレの口の中に放り込む。 途端に重ねられる唇、セフィロスの舌がオレの舌を捕らえた。 二人の体温で、溶けていくチョコ、苦味がかかった甘いカカオの風味が口一杯に広がる。 それをゆっくり味わう様に、セフィロスは更に舌を絡めてくる、チョコを味わっているのか…それとも… 頭あの中が真っ白になってくる。 どうしよう、ここ学校の中だっていうのに、オレ…我慢できそうにない…さっきから何度もチョコより甘いキスをされてるんだ、しょうがないだろう?セフィロス… それをセフィロスに伝えたくって、オレはもどかしい様に腰を振って、オレ自身をセフィロスに擦り付けた。 それを察した様にセフィロスの掌が、背中から腰のラインを滑る。 強弱を付けて絶妙にオレの弱い所を探っていく巧みな指先、官能をかき立てられる様なその動きが、たまらない。 もうキスだけでイッチャいそうだ… 口の中のチョコはほとんどなくなっていたけれど、貪る様にオレはさらに舌を絡めた。 その時聞こえた、幾人かのざわめき。 びくっとして離れようとしたオレの頭をセフィロスが押さえ付けた。 ちょっと待てよ!ばれたらまずいだろうが、離せよ!! ドンドンと胸を叩いて抗議するオレをしり目に、セフィロスはキスをしたまま、にっと笑うと、さらに強く抱き締めてきた。 がちゃがちゃとドアノブをまわす音、思わず背筋がびくっと強ばる。 「あれ?開かないよ、鍵かかってるみたい。」 「えー?電気ついてるのに、じゃあもう帰っちゃったのかな、クラウド君。」 何人かの女の子の声…鍵掛けてるなら、そう言えよ、焦っちゃったじゃないか。 でも、オレを探してるのか? 「あーあ、せっかく渡すチャンスだと思ったのに、今日一日先生と一緒だったから、渡すチャンスなかったんだよ。」 この声は、たしかオレの後ろの席の子だ。 「渡しちゃえばよかったじゃない。」 「だって、義理チョコじゃないもん、高校に行ってもつき合って、って言うつもりだったから…」 えー?そうだったのか、知らなかった… 思わず赤くなったオレを、唇を合わせたままのセフィロスが、ギロリと睨みつけた、そして、激しく舌を使いだす。 腰を彷徨っていた指先は、割れ目の間をズボンの上から抉る様に刺激しだした。 びくびくっと身体が痙攣したように強ばっていく。 ちょっと、セフィロス…そんなにしたらオレ、もう… 女の子達の気配がなくなって、セフィロスはすっかり力の抜けたオレの唇からゆっくりと離れた。 「まったく、今日一日あきらめの悪い事だ。」 ぼんやりとした頭がその言葉を捕らえて、はっとする。 「セフィロス、知ってたのか?あの子がオレにチョコくれようとしてたの。」 「他にも4、5人いたぞ、告白込みでおまえにチョコをやろうとしてた奴。」 そんな、もったいない…ん?と言う事は… 「ひょっとして、オレを一日膝の上に乗せてたのって、それを邪魔するためか?」 ちょっと不機嫌に問いつめるオレに、セフィロスはしれーっと答えた。 「あたりまえだ、だれがそんなチャンスやるもんか、オレのクラウドに。」 オレのクラウド…その響きがたまらなく嬉しい、でもちょっとイジワルしたくて、怒った振りして言ってみた。 「ずるいよ、自分だけたくさんもらって。」 「あれは全部、『義理』だろうが、そんなに欲しかったのか?」 ちょっと心配げなセフィロス。 「そりゃ、オレだって男だから、バレンタインに可愛い女の子からチョコもらいたかったよ。」 心配げなセフィロスの顔が、マジになってきた。 「本当に、本当に欲しかったのか?」 不安げに揺れる翡翠の瞳、普段あれだけ自信満々なのに、どうしてこうなんだろう、オレがあんた以外に心をうつすとでも思ってるの? 「…だったらすまん…」 返事をしないオレの態度をどうとったのか、苦虫を噛み潰した様な顔をしてセフィロスが謝る、ちょっと拗ねた? オレはセフィロスの唇にちゅっとキスをして笑った。 「そんなはずないだろう?オレはあんただけでいい、あんたからもらうだけでいい。」 「本当か?」 「あたりまえだろ?愛してるのはあんただけだ。」 ようやくほっとしたらしいセフィロスは、オレの髪をやさしく撫でた。 「オレもおまえだけを愛してる、ホテルでチョコを買ってやるから…」 言いかけたセフィロスにオレはもう一度ちゅっと音を立ててキスをした。 「いらない。」 「だって、おまえ…」 「チョコより、あんたが欲しい…」 言いながら、オレはセフィロスのズボンのベルトに手をかけた。 「クラウド…夕食の後でゆっくり…」 「そんなに待てない。」 かちゃかちゃと、ベルトを外しながらオレは答える。 「今すると、着替えに戻らないといけないぞ。」 「かまわないよ!」 「でもクラウド…」 どーしてあんたはこんな時、妙に常識人なんだ? 「うるさいな!さっきキスだけでイッチャッたから、もう一緒なんだよ!早くしようよ!それとも嫌か?」 気付いてなかったのかこのバカ!真っ赤になって答えたオレをセフィロスは嬉し気に抱き締める。 「嬉しくて目眩がしそうだ。」 ああ、そうかよ!…オレも嬉しいけど、そんな顔されると… ズボンのジッパーをおろそうとしたオレの手を外し、セフィロスが学ランのボタンを外し始める。 シャツのボタンを外しながらめくり上げ、ズボンの中に手を這わされた。 「濡れてるな、しっかりと。」 「ったりまえだろ…責任とれよ…」 直接的な刺激に背を仰け反らせながらオレは答えた。 「…ワルイ子だ…」 ニヤッと笑ったセフィロスが、オレの胸に唇を這わせだす。 そうだよ、オレあんたといると段々悪い子になっていくよ、学校の中でこんな事して平気なんて…でも… いいんだ…だって… あなただけを愛してるから… オレは大きく震えた、喜びを噛み締めて… top |
||||||||